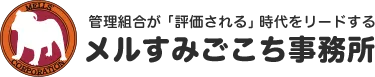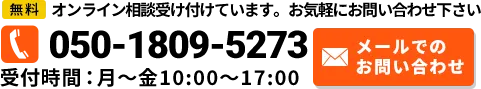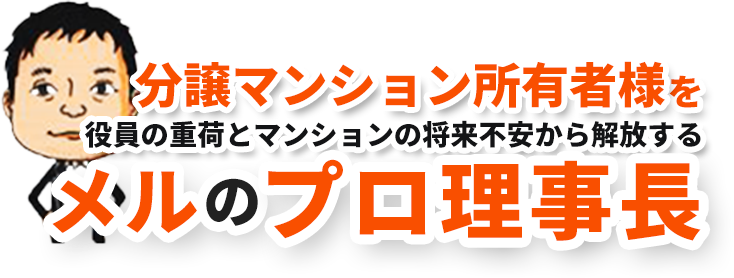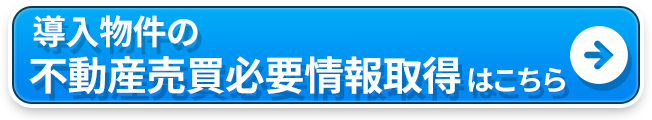“管理規約の見直し”に悩んだら 〜実際の相談事例から学ぶ、ムリなく始める規約改正〜
こんにちは。
マンション管理士として日々管理組合を支援している、㈱メルすみごこち事務所の武居です。
先日、行政支援の相談会にて、ある管理組合から
「管理規約を見直したいが、どこから着手すべきか」
というご相談を受けました。
とても前向きで熱心な理事会・委員会の方々でしたが、実際に手を付けようとすると、
「検討ポイントが多すぎて判断が難しい」
というお悩みを抱えていました。
この相談は、2025年の区分所有法等を踏まえて「マンション標準管理規約」が大幅に改正される、というタイムリーな話題であり、多くの管理組合役員の皆さまにも共通する課題だと感じましたので、現場で得た気づきを共有させていただきます。
1)規約は”わがまちの憲法” 住民が理解しやすい「理念を示す」
今回の管理組合では、規約内容を今後のマンション像に合わせてアップデートしたいという意向がありました。
その中でまず、お伝えしたのが、
- 規約の語尾を「です/ます」調に
- 前文にマンションの大切にしたい方向性を記載
という点。
前文には、
「このマンションは緑地を守りながら、良好な住環境を維持する」
といった理念を書き込むことで、住民の”自分ごと感”を高めることができます。
「です/ます」調と合わせて、規約を身近に感じてもらうことが“規約が活きる第一歩”です。
2)専有部リフォームの承認は専門性がカギ——委員会×細則活用
内容で最も議論が深まったのが、専有部分リフォームの扱いです。
築20年を過ぎ、フルリフォームが増えている現状の課題は以下のとおりです。
- 承認内容どおり施工されているか
- 周辺住戸への迷惑
- 工事車両の管理
そこでお伝えしたのは
- 技術者が確認する委員会を設置し*
- 詳細は細則で定める
という考え方。
理事会だけで判断しないことで、公平性が保たれ、役員の負担も軽減できます。
理事会=「最終判断」
審査 =「専門委員会」
といったように役割を分けることで運用が安定します。
*当マンションは世帯数も多く、技術系の専門の方が組合員にいて積極参加が見込まれるという状況があります。
3)ミュニティ活動は防災力向上の基盤——規約明記で正当性を
2016年3月の標準管理規約の改定以来、「コミュニティ活動が管理費で行えるのか?」という相談を受けることがよくあります。
今回の事例でも、
自主防災・防犯活動を目的に
コミュニティ活動を規約に位置付けたい
とのご意向がありました。
結論としては、
- 規約に「コミュニティ活動」を明記可能
- コミュニティ委員会を設置する方法が一般的
との助言を行いました。
防災力向上という明確な目的があれば、コミュニティは”単なる交流”ではなく安全性の担保につながります。
4)理事会運営は「責任主体」を明確に——任期・代理出席の整理
今回課題となったのは
- 任期を巡る不公平感
- 代理出席制度
です。
こちらのマンションは「できれば2年続ける」「家族なら誰が出席しても良い」と言うような規約で、任期も出席者も選べるような曖昧な記述となっていました。
これに対して私が助言したのは以下の2つの方針です。
- 任期は「2年」と明確に
- 代理出席は削除*
総会決議により選出された理事について、代理出席を認める規定は不適切です。
理事の代理出席は、責任の所在を曖昧にし、運営の透明性を損ねるリスクがあり、裁判例でも否定的に扱われています。
そこで、
誰が理事に就任できるのか
“表で整理する”ことをおすすめしました。
日本語の運用に委ねるより視覚的に整理することで、文字だけで書いた場合よりトラブルが起きにくくなります。
*2025年10月に改正された標準管理規約にも、代理人に関する考え方が触れられています。今回のアドバイスは標準管理規約の改正前に行ったものですが、「役員として活動するのが家族の誰なのか」を明確にしておくという趣旨において同じです。
5)附則の見直しで規約の読みやすさを確保——不要条項は大胆整理
今回は
- 町会加入条項
- 専用庭・ルーフバルコニー使用料の扱い
なども見直し対象でした。
特に町会加入は、すでに裁判・国の見解でも管理組合が強制すべき業務ではないため削除をおすすめしました。
また、使用料等の具体的金額は、条件や運用が変わる可能性もあり、その時に柔軟な変更が可能になるよう規約ではなく、細則で規定する方が合理的です。
ほかにも、入居時の規定、例えば、修繕積立基金など、この先の管理組合運営に全く関係のない項目が残っていると混乱を招きかねず、「規約嫌い」を助長してしまいます。
不要な項目は、思い切って削除した方がいいとお伝えしました。
現場で強く感じた “3つのポイント”
| 視点 | コメント |
|---|---|
| ① 規約は”住民のもの” | 理念があると動きやすい |
| ② 細則を使う | 改正しやすく、柔軟運用ができる |
| ③ 専門性を外に求める | 理事会の負担を減らし、客観性・公平性を高める |
おわりに
今回の相談を通じて改めて感じたのは、規約改正は「一気に完璧」を目指す必要はないということです。
まずは
- 想いの言語化(前文)
- 修繕や防災など課題の優先付け
- 細則・委員会の活用
から始めると、管理組合運営がの改善を実感しやすく、その後の改定にも弾みがつきます。
管理規約は
マンションの未来を守る”資産”です。
「気になるところから、少しずつ」
が成功の近道だと感じています。
さらにお困りの方へ
実際に規約を改定する際には、最新の標準管理規約への準拠や理事会・総会での説明資料づくりなど、かなりの作業量を伴うため、私たちも業務として報酬をいただきながら丁寧に伴走しています。
一方で、
「方向性のアドバイス」だけであれば、
いつでもお気軽にご相談いただけます。
- どこから着手すべき?
- この方針で進めて大丈夫?
- 専門家に一度だけ見てほしい
——そんな段階でも、まずは当社の無料相談をお気軽にご活用ください。
無料相談こちら >>