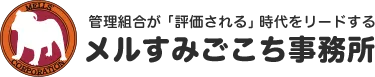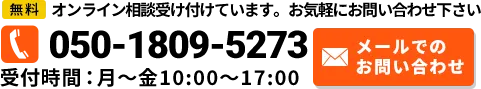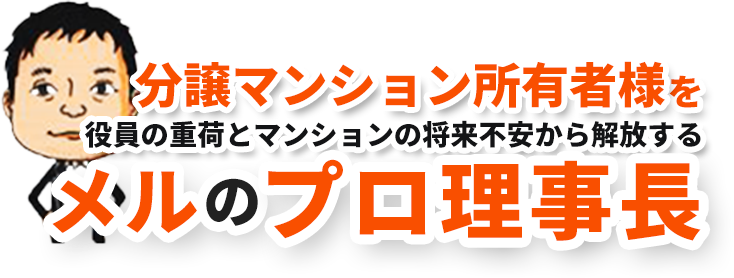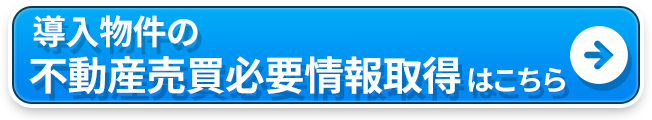2025年、管理会社はもう選べない?この変革期にどう備えるのか!
今年の最初のコラムは、今後のマンション管理会社について考えてみました。
もはや管理会社に管理を委託している管理組合では、管理委託費の値上がりに直面していないマンションはないと思います。現在、管理会社は人手不足が深刻化しつつあり、2025年以降からはその状況もより顕著化していきます。
管理組合は、より賢く運営していかないと費用面でも管理面でも厳しい時代に入ります。
管理会社の経営課題
もう5年以上経ちましたが、いわゆる住建ショックと言われる住友建物サービス社が、大量の管理組合との契約を継続しなかった(全国で200棟以上とも言われています)事は記憶に強く残っています。
この事件?は、管理会社が受託できる管理組合数を超えたことと、それに伴い管理会社が大きく方針を変えた事案として業界では認識されています。
それまでは管理業界は、管理物件数を増やせば売り上げも利益も伸ばすことが可能と考えられていて、自ら契約を終了するという選択肢は考えられませんでした。そのため委託費はそこそこでも契約数を伸ばすことに注力していました。
ところが、受託可能数が限界に来たため、業績を伸ばすためには管理物件の採算性を重視するという方向に管理会社が舵を切ることとなりました。管理会社が物件ごとの採算性を重視する方向に舵を切れば、一定の利益がなければ管理会社は引き受けないため、委託費は値上がりしていきます。
さらに、最近は管理会社の担当者が離職すると補充(新規採用)できないことが多くなってきています。管理会社はもともと人気業種ではないため、給与面での魅力がない限り新たな人材を採用することが難しいといえます。仮に給与面を手厚くしようとするならば、当然これは管理委託費に反映されます。したがって、管理委託費の値上がり材料の一つでもあります。
さらに管理会社の都合を深掘りしてみますと、1人のフロント担当者が担当できる棟数(管理組合数)は限られており、フロント担当者は増えない、物件は抱えきれないとなれば、同じ棟数で売り上げが大きくなりやすい、規模の大きいマンションに注力していくこととなります。
中小規模のマンションでは、管理会社の採算性が良くても、管理会社に入る委託料の絶対額は多くありませんから、今後100世帯未満の物件では、管理会社への委託費は規模の大きなマンションより割高になることは間違いありません。
清掃員や管理員の大幅な人手不足
10年前までは60歳以上の再雇用先として、清掃員や管理員に応募する人員が多くいました。しかしながら、定年が65歳になったことにより、実際に65歳を超えてから応募してくる人材は極端に減っています。対象となる人口層の変動よりも、明らかに求職者が減っているという状況です。
退職後1、2年ゆっくりしてから管理員や清掃員をしようかというこれまでのパターンが、その時に62歳なのか67歳なのかによって、選択肢が変わってきているということでしょう。
主な募集窓口となるハローワークに聞いても、条件(金額や、勤務時間)が合わないというものではなく、応募がないという回答が最も多いようです。
今後は、政府は企業に対して70歳までの継続雇用を推奨し、企業側も定年を廃止するなどの動きが広がりつつある状況を鑑みると管理員、清掃員の人手不足はより深刻になるでしょう。
管理員を雇えるマンション=高級マンションという図式も遠くありません。
マンション管理のDX化への課題
昨今巷でDX化による業務効率と生産性の向上ということが言われています。
当然管理会社もこれを試みていますが、建物という現地に行かないと見られないもの、使い方を理解していない素人の相手をする事なので、どうしても人手を削ることに限界があります。
居住者、区分所有者は色々なルールを理解している前提であれば、管理会社の業務はかなりDX化により進むと考えられます。
一方で、現実はマンションのルールや使い方に対して区分所有者や居住者は無頓着で、仮に問い合わせの回答をHPのQ&Aにわかりやすく書いても、それを探すキーワードさえ選べないというのが実態です。
管理会社の苦労は、「提出される書類の不備を追いかける」ことではなく、「提出してこない人を追いかける」ということに尽きます。つまり、同じことをルーティンのようにこなしているように見えますが、彼らの苦労のほとんどは不良区分所有者に翻弄されていると言えます。
いずれAIが解決してくれそうな光明も見えつつあるものの、「今目の前にある人手不足の危機」をDX化だけでは解決できる状況ではありません。
管理組合側の事情
もともと分譲マンションというのは、社会人になってすぐに買えるわけではなく、一般的には40歳前後早くても35歳くらいが一時取得層です。そこから20年が経過したマンションは、平均年齢が50代後半となり30年経過すると60代後半と言うことになります。管理組合の平均年齢は、スタートが中年なので、区分所有者の高齢化率は、世間の高齢化と比べると圧倒的に早くなります。
現在、築50年のマンションで起こっている事は、旧耐震である建物の課題、を除けば高齢化による役員のなり手不足です。ただし、この世代くらいまでは、ボランティア精神も高く、マンションと言う共同住宅において、役員を順番にしていくということに抵抗の少ない世代でした(その証拠に昔は自治会も機能していた)。
それでも役員の成り手が不足するのです。
一方、現在の50代から60代については、マンションは戸建てと異なり、プライバシーが守られると言って販売された世代です。そのため、役員にならなければいけないと言う義務感は薄く、それが役員のなり手不足に拍車をかけます。
また、多様性が認められて行く時代というのは一般には望ましいことかもしれませんが、マンションは必ずしも多様性を享受できるものではありません。
共用部分や共用施設の使い方やルール設定は一つの決まりを同じように全員が遵守しなければなりません。物事に対してお金を払って外部に委託したい人と、節約して自分たちが順番に責任を持ってやっていきたい人の考えは、相容れないものの、上手く調整しなければなりません。
多数決で決める仕組みしかない管理組合では、結果に対してどちらかまたは双方に、遺恨というひび割れを残す可能性があります。その時のひび割れは小さくても、時間の経過とともに議論が再燃する事はよくあり、管理組合の運営を難しくしていきます。
さらに区分所有法の改定や複雑化する管理や業界の動きに追従するためには、高齢化したマンションには限界があります。

管理組合の誤解
管理会社がなければ管理できないから政策が助けてくれるという声を聞くことがあります。
一般には日常生活において困ったことや国の方針に沿って行けるように補助や支援体制を築いていくのが行政の仕事です。マンションも高経年化に伴い、何らかの支援があるのではとの声も聞かれますがこれは大間違いです。
まず、マンションに居住している割合が高いのは都市部に過ぎず、全国では人口の10%程度にしか過ぎません。一部の市区では、行政窓口にマンション課のような窓口がありますが、これは例外的です。
また、分譲マンションは資産ですから、そもそも行政としては、資産を持てる層に対する補助を考えるより、もっとお金を優先的に使うべきところがいくらでもあります。
そういった意味で、東京23区や大阪の一部のように居住者の過半がマンションに住んでいるというような地区では、多少なりとも行政の関与する可能性はあるものの、かなり限定的であると思っておいた方が良いでしょう。
行政の目線では、管理不全で建物が放置され、廃墟化したり地震で旧耐震の建物が倒れて救助に支障があったらどうするかを心配しているだけです。管理組合運営に直接興味があるわけではありません。
分譲マンションはどこまでも自助努力が求められるので、安易な発想は危険で、自らの管理組合運営をどうしていくべきか、区分所有者は真剣に考え続けなければなりません。これらの事情から、100世帯未満、特に50世帯を切るマンションでは、今後管理会社に管理委託することが非常に割高になります。
また、引き受け可能数が限界にあるため以前は『高ければ、サービスが悪ければという理由で管理会社を変える』という選択肢が管理組合にはありましたが、変えたくても変えられない、引受先がないという現象が起こりつつあります。
管理委託費の上昇は続き、管理会社の選択が厳しくなると言う状況の中、管理組合は今後どうすれば良いのかを考える年、それが2025年ではないでしょうか。